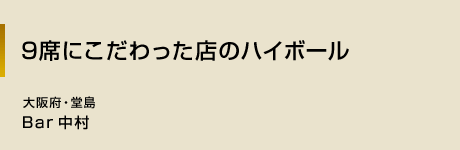- TOP >
- 記事・レポート >
- 噂のバーと、気になる一杯 >
大阪府・堂島 Bar中村
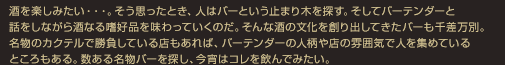
単純ゆえに差が出る流行の酒
ウイスキーの旨さがわかるハイボールが飲みたい!そう思うといてもたってもいられなくなり、北新地の堂島上通りを急いだ。「神田川本店」の隣のビルにある「Bar中村」は最近見つけた店である。このバーのマスター・中村仁是さんは現在34歳、この世界ではまだまだ若手の部類だろうか。 中村さんは浜松の出身。18歳の時に料理人になろうと大阪へやってきて、中之島の辻学園調理技術専門学校で学んだ。バーテンダーになろうと思ったのは2年目の専門課程でのこと。調合する魅力に取りつかれ、卒業後には「バーK」(北新地)の門を叩いていた。その後、銀座のバーでも修業し、地元・浜松で店を持とうと帰省した。しかし、その時、目にしたものは都会と地方の格差。昔より華やかさを失った町は、ネオンの数が確実に減少していた。そこで中村さんは再び北新地に舞い戻って来る。何軒かの店で働いたのちに、09年の12月に自分の店を持つに至った。
オープンしてまだ半年足らずの真新しいカウンター席に腰かけ、「ハイボールが飲みたいんだけど…」と私はおもむろに注文した。昨今はハイボールがブームである。どんな店でもそれをメニュー化して売っている。今回のブームの火付け役となっているのが「角瓶」だ。これをベースにソーダで割ったものを、若い世代はさも新しいカクテルのように飲んでいるそうだ。 注文すると、中村さんは、「響12年」を取り出し、それをグラスに1ジガー(45ml)注いだ。「響12年で作るんですね」と話しかけると、「これがうちのハウスウイスキーなんですよ」と言う。「ハイボールを」とだけ言う人には、この店では「響12年」を使って作るのだそうで、常連客からはその味はすでに認知されているらしい。中村さんは「響12年」を注ぐと、そこに氷とソーダ100mlを入れて軽妙にかき混ぜる。仕上げには「響12年」のミニボトルスプレーを2〜3回吹きつけてウィスキーの香りづけを施す。「こうすることで、香りづけにもなりますし、何よりこのスプレーが話のネタになるんですよ」とにっこり笑ってハイボールを差し出した。私は長年、料理の取材を行っている。そこで見つけたことは単純なものほど難しいという事実。だから日本料理の職人は、「澄まし椀の味で料理を評価して欲しい」とよく言うのだ。ハイボールもベースは市販のウィスキー、それをソーダで割るだけの作業だが、作り手によってかなりの差が出る。
「響12年というウィスキーは、香り豊かな上にしっかりした骨格があるんですよ。だから延ばしても崩れない。そこがハイボールに向いているんですよね」と中村さんは「響12年」の特性を説明してくれた。「実は、他所ではビールとハイボールしか飲まないんですが、そんな私がテイスティングした時にこれを使おうって決めたくらいです。それくらいこの酒はハイボールに適していますね」と話す。確かに私の周りでは、まだこの酒の特性を知らない人がいる。「響17年」がすこぶる繊細で高価なものだけに「響12年」を同じイメージで捉え、「ソーダで割るのがもったいない」と言う人までいる。しかし、中村さんの言うように「響12年」にはしっかりした味わいがあるのは事実。そのため、混ぜても持ち味を失するいことがないのだ。だから私も周囲に「響12年」のハイボールを薦めている。「私はお酒をどんなもので割ってもいいっていう考え方を持っているんです。極端なことを言えば、赤ワインの氷入りだってOKなんですよ。お客さんが飲みたいというスタイルを拒む権利は誰にもありません。ただ30年前のウィスキーを水割りにするとボケることもあるんです。そんな時はアドバイスとして声がけしているんです」。
9席にこだわる理由とは…
「バー中村」は、カウンター席のみで、たった9席と小ぶりな店である。しかし中村さんは「私のキャパでは、これが精一杯」と言う。そして来店客に一人ひとりと、話しながらバータイムを楽しんでもらうスタイルを貫いている。だから9席―。この目が届く範囲が中村さんの真摯な姿勢を物語っている。
そんな中村さんの意図が伝わっているのか、17時からやって来る人が多い。夕方の来店客は1〜2杯をここで飲んで家路に着く。19時ぐらいからは本格的に飲もうという客が訪れる。こうして「Bar中村」は、客足が絶えることなく稼動しているのだ。
34歳の中村さんにとっては、客の大半が年上の人。バーという形態はマスターと同じような年頃の人が集まるものだが、ここは北新地なので当然ながら中村さんより年長の客が多くなる。「だからと言って甘えては失礼」と中村さんは言う。真面目に人と接し、酒を飲む時間を楽しんでもらいたい。そのためには2人連れの3組が理想だと付け加える。
こんな話をしているうちに「響12年」の甘さが舌に伝わり、すでに何杯めかを味わってしまった。すると、中村さんは「1杯目と4杯目では味が違うんですよ」と語りかけて来た。人は杯を重ねるほど酔っていく。だから1杯目に旨いと思ったものでも、数杯目には異なった味に思えてしまうものだ。中村さんは同じハイボールでも1杯目と同じ旨さを出すために分量をちょっとだけ変えていく。
こうして調整することで味の変わらぬハイボールが実現するのである。「どんなルートでこの店へ来たのかなど、私はお客さんとできるだけ話をすることにしています。和食を食べて来た人と中華を味わって来た人では、自ずと求める味も変わるんですよ」。そうまでしないと、嗜好品は売れないそうだ。それだけバーは難しい商売だと中村さんは話してくれた。
この店の常連でバーボンソーダしか注文しない人がいる。その人に中村さんはある日、「響12年」のハイボールを薦めた。するといつしかその客はバーボンと「響12年」を併用し始めた。頑なに自分の嗜好を変えなかった人にまで影響を与えてしまった「Bar中村」のハイボール。これを飲まずして、ハイボールの旨さは語れないだろう。
Bar中村

- 住所大阪市北区堂島1−2−25谷安フォースビル2階
- TEL06-6342-6342
- 営業時間17:00〜翌1:00(土曜は〜0:00まで)
- 定休日日・祝日